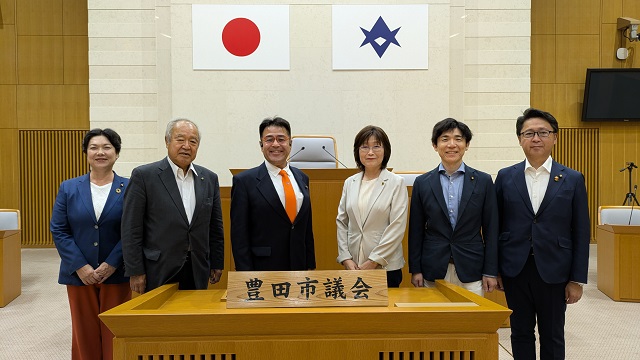���݈ʒu �F�g�b�v�y�[�W › �s�����@��
�e��C�ψ���A�c��^�c�ψ���A�e��h�@�s�����@��
���@��
- �ψ���E��h��
- �����ψ���
- ���@��
- ���m���@�L�c�s
- ���@��
- DX���i�̎��g�݂ɂ���
- ���{��
- �ߘa6�N10��25��
- �Q���Ҏ���
���@���ʊT�v
�i1�j���@��̊T�v
�@�L�c�s�͈��m���̂قڒ����Ɉʒu���A���m���S�̂�17�D8�����߂�L��Ȗʐς����܂��ŁA�l����415�C863�l�i�ߘa6�N4��1�����݁j�A�ʐς�918�D32㎢�ł��B
�@�S���L���̐����i�o�z���ւ�u�N���}�̂܂��v�Ƃ��Ēm���A���E�����[�h����A���̂Â��蒆���s�s�Ƃ��Ă̊��������A�s��̂��悻7�����߂�L���ȐX�сA�s����т�����A�G�߂̖��ʕ������点��c�����L����A�b�ݑ����̂܂��Ƃ��Ă̊�������Ă��܂��B���ꂼ��̒n��̎����������A���l�ȃ��C�t�X�^�C����I���ł��閞���x�̍����s�s�Ƃ��āA����Ȃ鐬����ڎw���Ă��܂��B
�i2�j���@���e
������܂ł̎�Ȍo��
���ߘa2�N�x
�E���헪�ۂ�ݗ����A���t�{����DX���l�ނ�z�u�i�`���݁j�i4���j�B�I�����C����c�����i5���j�A�����`���b�g�����i7���j�AAI�|OCR�EAI�`���b�g�{�b�g�����i11���j�B�f�W�^�����x���헪������B�f�W�^�������i�{����c�A�f�W�^�������i�`�[����ݒu�BAI�c���^�����i2���j�B
���ߘa3�N�x
�E�f�W�^�������i�S�����āi��CDO�j��ݒu�i8���j�BRPA�����i11���j�B
���ߘa4�N�x
�E�L���g�[�����؊J�n�i4������1�N�ԁj�B�f�W�^�����x���헪������i9���j�BLINE�iBotExpress�j�}�C�i�|�C���g�\��i1���j�B
���ߘa5�N�x
�E�L���g�[�������J�n�i6���j�B�EDX���Ɛl�ފm�ہiCDO�⍲���j�i8���j�B����AI�����`�[����ݒu�i10���j�B
���ߘa6�N�x
�E����AI�K�C�h���C��������i5���j�BLINE�iBotExpress�j�e�傲�ݗ\��i10���j�B
����g���j
�@�����������̐��i
�@3�N��̏������𒅎��Ɏ���������B�������ՂƂ��āA10�N��̏������ɋ߂Â��Ă����B�e�[�}�́u�������A�b�v�f�[�g�v�u���������N�_�Ɋ����A�g�v�u�{�Ȓ��\�Z�A���Ԏ��{���p�v
�A�O�ꂵ��DX�E�Ɩ����v
�@�����c�[����O��I�Ɋ��p���A�e���ǁE�e�ۂ̎����^�Ŏ������v�iBPR���j��O�ꂵ�ADX�𒅎��Ɏ��s����B�e�[�}�́u�s���T�[�r�X����v�u�X�}�[�g�����v�u���������v�v�u�Ɩ����v�v
�BDX�~�����A�g
�@�I�[�v���f�[�^�����p���������A�g�𑣐i����B���ԂƂ̘A�g�̓V�X�e���Ȃǂ����ł͂Ȃ��A�l�ޖʂł��A�g���A�e���ǂ̏�����������������B�e�[�}�́u�I�[�v���f�[�^�v�u�{�Ȓ��\�Z�A���Ԏ��{���p�v
���i���E����
�E�葱�i��360�葱�j�̃I�����C�����́A�ڕW�l�ł���100����B�����錩���݁i�@�ߓ��őΉ���������́i�ΏۊO�j���܂ޏꍇ�̐i������80���j
�E�L���b�V�����X���ς̓������́A�ڕW�l�ł���80����B�����錩����
�E�I�[�v���f�[�^�́A�ڕW�l�ł���300�`500��B�����錩����
�E�e��c�[���iAI�`���b�g�{�b�g�AAI-OCR�ARPA�A�L���g�[���A����LINE�j�̓����E���p
�E�X�}�[�g�����V�X�e���̓����i�Z���ٓ��͂́u�����Ȃ������v��ߘa5�N6���ғ��j
�EBPR�i�Ɩ��������j��10��25�Ɩ��ŁA�Ɩ��ϑ��ɂ��e�ۂ�BPR���^�Ŏx��
���ۑ�
�����̒��̃g�����h�ւ̑Ή�
�E�_�C�o�[�V�e�B�i���l���j�A�A�N�Z�V�r���e�B�i���p�̂��₷���A�֗����j�A�ڋq�T�[�r�X�̃p�[�\�i���C�Y�i�ڋq��l�ЂƂ�̗v�]��j�[�Y�ɍ��킹�ăT�[�r�X��j�A�f�[�^�A�g�E�f�[�^�����p�E�f�W�^�����
���s�����̉ۑ�
�E�l�����ɂ��A�E���������R�Ɍ����\�z�����B����̃T�[�r�X�������ɂ���10�N��A20�N����������邩�B�ʏ�Ɩ��Ŏ��t�̏�
������܂ł̎�g�Ō����Ă���������
�E�s���ڐ��ł́A����܂ł́u���I�ȑΉ��v����A�u�j�[�Y���������Ή��v�ցB�s�����f�W�^���ƃA�i���O��I���\�����ɁB���̓A�i���O��������������Ȃ����A�����I�ɂ̓f�W�^����̂�
�E�E���ڐ��ł́A�������[�`�����u�A�i���O��́v����A�u�f�W�^����́v��
���S�̓I
�E�꒩��[�Ɏ���������̂ł͂Ȃ����A������n�߂Ȃ���Ύ�x��ɂȂ�i10�N��̍��̂܂܁j�Ƃ�����@�������K�v������
�i3�j���@���瓾��ꂽ�l�@
�@�f�W�^�����̐i���Ǝs���T�[�r�X����̃o�����X
�@�L�c�s�ł́A�f�W�^������i�߂邱�ƂŎs���T�[�r�X�����コ������g�݂��s���Ă��܂��B�A�i���O�ƃf�W�^����I�ׂ�������A�Z���j�[�Y�ɑΉ����邱�Ƃ��ۑ�ƂȂ��Ă��܂��B
�@�{�s�ł��A�I�����C���T�[�r�X�����邱�Ƃ͏d�v�ł����A�f�W�^�����ɑΉ��ł��Ȃ��s���w����萔���݂��Ă��܂��B���ɁA����҂�f�W�^���ɕs����Ȏs���Ɍ������x�����������邱�Ƃ����߂��܂��B
�A�E���̋Ɩ����v�ƃf�W�^�����̒蒅
�@�L�c�s�́ARPA�i���{�e�B�b�N�E�v���Z�X�E�I�[�g���[�V�����j��AI-OCR�Ȃǂ����A�Ɩ��̌�������i�߂Ă��܂��B���ɁA�����Ɩ��̃f�W�^�����ƂƂ��ɁA�E���̕��S�y����ڎw���Ă��܂��B�u�E�����̌����ɔ����A���s�Ɩ��̃f�W�^�������K�{�ƂȂ邽�߁A���̂��߂̎x���̐����ǂ��m�ۂ��邩�v���ۑ�Ƃ��ċ������Ă��܂��B
�܂��ADX���i�̂��߂̐��E���iCDO�j��ݒu���A�O�����畛�Ɛl�ނ���Ƃ��m�ۂ���ȂǁA�����A�g�ɂ�鋭���l�ނ��}���Ă��܂��B�Ɩ����v��f�W�^���c�[���̊��p���x����d�v�ȗv�f�ƂȂ��Ă��܂��B
�@�{�s�ł��A�Ɩ��������̂��߂̃f�W�^���c�[�������͕K�{�ł��B���ɁA�{�s�͐E�������������̂ɔ���Ȃ��ł��B�����I�ɋƖ��𐋍s���邽�߂ɂ́AAI��RPA�Ȃǂ�ϋɓI�ɓ������A�E���̕��S���y�����邱�Ƃ͂ƂĂ��d�v�ł��B�܂��A�f�W�^�����ɑ���E���̋���E�x�����p���I�ɍs���A�X���[�Y�ɐi�߂邽�߂̑̐��\�z�����߂��܂��BDX���i�̂��߂ɐ��I�Ȓm�������l�ނ��m�ۂ��A�K�v�ɉ����ĊO���̐��Ƃ▯�Ԋ�ƂƘA�g����d�g�݂𐮂���ׂ��ł��B�f�W�^���X�L�������ړI�Ƃ������C�v���O���������������A�����ł�DX���i�̐����\�z���邱�Ƃ��K�v�ł��B
�B�����A�g�ƃI�[�v���f�[�^���p�̐��i
�@�L�c�s�ł́A�I�[�v���f�[�^�̊��p�▯�ԂƂ̘A�g��ϋɓI�ɐ��i���Ă���A����ɂ��s���T�[�r�X�̌����V�������Ƃ̏ꂪ���܂�Ă��܂��B�s�����T�d�ȉۑ�̉����ɉ����������܂��B
�{�s�ł��A�I�[�v���f�[�^�̊��p�▯�Ԋ�ƂƂ̘A�g���������邱�Ƃ͗L�v���ƍl���܂��B���ɁA�f�W�^���Z�p�ɋ������Ԋ�ƂƂ̋��͂́A�V�����T�[�r�X������I�ȍs���^�c�̃��f����n�����A�s���ɂƂ��ėL�v�ȏ�����邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂��B
�@�L�c�s�͈��m���̂قڒ����Ɉʒu���A���m���S�̂�17�D8�����߂�L��Ȗʐς����܂��ŁA�l����415�C863�l�i�ߘa6�N4��1�����݁j�A�ʐς�918�D32㎢�ł��B
�@�S���L���̐����i�o�z���ւ�u�N���}�̂܂��v�Ƃ��Ēm���A���E�����[�h����A���̂Â��蒆���s�s�Ƃ��Ă̊��������A�s��̂��悻7�����߂�L���ȐX�сA�s����т�����A�G�߂̖��ʕ������点��c�����L����A�b�ݑ����̂܂��Ƃ��Ă̊�������Ă��܂��B���ꂼ��̒n��̎����������A���l�ȃ��C�t�X�^�C����I���ł��閞���x�̍����s�s�Ƃ��āA����Ȃ鐬����ڎw���Ă��܂��B
�i2�j���@���e
������܂ł̎�Ȍo��
���ߘa2�N�x
�E���헪�ۂ�ݗ����A���t�{����DX���l�ނ�z�u�i�`���݁j�i4���j�B�I�����C����c�����i5���j�A�����`���b�g�����i7���j�AAI�|OCR�EAI�`���b�g�{�b�g�����i11���j�B�f�W�^�����x���헪������B�f�W�^�������i�{����c�A�f�W�^�������i�`�[����ݒu�BAI�c���^�����i2���j�B
���ߘa3�N�x
�E�f�W�^�������i�S�����āi��CDO�j��ݒu�i8���j�BRPA�����i11���j�B
���ߘa4�N�x
�E�L���g�[�����؊J�n�i4������1�N�ԁj�B�f�W�^�����x���헪������i9���j�BLINE�iBotExpress�j�}�C�i�|�C���g�\��i1���j�B
���ߘa5�N�x
�E�L���g�[�������J�n�i6���j�B�EDX���Ɛl�ފm�ہiCDO�⍲���j�i8���j�B����AI�����`�[����ݒu�i10���j�B
���ߘa6�N�x
�E����AI�K�C�h���C��������i5���j�BLINE�iBotExpress�j�e�傲�ݗ\��i10���j�B
����g���j
�@�����������̐��i
�@3�N��̏������𒅎��Ɏ���������B�������ՂƂ��āA10�N��̏������ɋ߂Â��Ă����B�e�[�}�́u�������A�b�v�f�[�g�v�u���������N�_�Ɋ����A�g�v�u�{�Ȓ��\�Z�A���Ԏ��{���p�v
�A�O�ꂵ��DX�E�Ɩ����v
�@�����c�[����O��I�Ɋ��p���A�e���ǁE�e�ۂ̎����^�Ŏ������v�iBPR���j��O�ꂵ�ADX�𒅎��Ɏ��s����B�e�[�}�́u�s���T�[�r�X����v�u�X�}�[�g�����v�u���������v�v�u�Ɩ����v�v
�BDX�~�����A�g
�@�I�[�v���f�[�^�����p���������A�g�𑣐i����B���ԂƂ̘A�g�̓V�X�e���Ȃǂ����ł͂Ȃ��A�l�ޖʂł��A�g���A�e���ǂ̏�����������������B�e�[�}�́u�I�[�v���f�[�^�v�u�{�Ȓ��\�Z�A���Ԏ��{���p�v
���i���E����
�E�葱�i��360�葱�j�̃I�����C�����́A�ڕW�l�ł���100����B�����錩���݁i�@�ߓ��őΉ���������́i�ΏۊO�j���܂ޏꍇ�̐i������80���j
�E�L���b�V�����X���ς̓������́A�ڕW�l�ł���80����B�����錩����
�E�I�[�v���f�[�^�́A�ڕW�l�ł���300�`500��B�����錩����
�E�e��c�[���iAI�`���b�g�{�b�g�AAI-OCR�ARPA�A�L���g�[���A����LINE�j�̓����E���p
�E�X�}�[�g�����V�X�e���̓����i�Z���ٓ��͂́u�����Ȃ������v��ߘa5�N6���ғ��j
�EBPR�i�Ɩ��������j��10��25�Ɩ��ŁA�Ɩ��ϑ��ɂ��e�ۂ�BPR���^�Ŏx��
���ۑ�
�����̒��̃g�����h�ւ̑Ή�
�E�_�C�o�[�V�e�B�i���l���j�A�A�N�Z�V�r���e�B�i���p�̂��₷���A�֗����j�A�ڋq�T�[�r�X�̃p�[�\�i���C�Y�i�ڋq��l�ЂƂ�̗v�]��j�[�Y�ɍ��킹�ăT�[�r�X��j�A�f�[�^�A�g�E�f�[�^�����p�E�f�W�^�����
���s�����̉ۑ�
�E�l�����ɂ��A�E���������R�Ɍ����\�z�����B����̃T�[�r�X�������ɂ���10�N��A20�N����������邩�B�ʏ�Ɩ��Ŏ��t�̏�
������܂ł̎�g�Ō����Ă���������
�E�s���ڐ��ł́A����܂ł́u���I�ȑΉ��v����A�u�j�[�Y���������Ή��v�ցB�s�����f�W�^���ƃA�i���O��I���\�����ɁB���̓A�i���O��������������Ȃ����A�����I�ɂ̓f�W�^����̂�
�E�E���ڐ��ł́A�������[�`�����u�A�i���O��́v����A�u�f�W�^����́v��
���S�̓I
�E�꒩��[�Ɏ���������̂ł͂Ȃ����A������n�߂Ȃ���Ύ�x��ɂȂ�i10�N��̍��̂܂܁j�Ƃ�����@�������K�v������
�i3�j���@���瓾��ꂽ�l�@
�@�f�W�^�����̐i���Ǝs���T�[�r�X����̃o�����X
�@�L�c�s�ł́A�f�W�^������i�߂邱�ƂŎs���T�[�r�X�����コ������g�݂��s���Ă��܂��B�A�i���O�ƃf�W�^����I�ׂ�������A�Z���j�[�Y�ɑΉ����邱�Ƃ��ۑ�ƂȂ��Ă��܂��B
�@�{�s�ł��A�I�����C���T�[�r�X�����邱�Ƃ͏d�v�ł����A�f�W�^�����ɑΉ��ł��Ȃ��s���w����萔���݂��Ă��܂��B���ɁA����҂�f�W�^���ɕs����Ȏs���Ɍ������x�����������邱�Ƃ����߂��܂��B
�A�E���̋Ɩ����v�ƃf�W�^�����̒蒅
�@�L�c�s�́ARPA�i���{�e�B�b�N�E�v���Z�X�E�I�[�g���[�V�����j��AI-OCR�Ȃǂ����A�Ɩ��̌�������i�߂Ă��܂��B���ɁA�����Ɩ��̃f�W�^�����ƂƂ��ɁA�E���̕��S�y����ڎw���Ă��܂��B�u�E�����̌����ɔ����A���s�Ɩ��̃f�W�^�������K�{�ƂȂ邽�߁A���̂��߂̎x���̐����ǂ��m�ۂ��邩�v���ۑ�Ƃ��ċ������Ă��܂��B
�܂��ADX���i�̂��߂̐��E���iCDO�j��ݒu���A�O�����畛�Ɛl�ނ���Ƃ��m�ۂ���ȂǁA�����A�g�ɂ�鋭���l�ނ��}���Ă��܂��B�Ɩ����v��f�W�^���c�[���̊��p���x����d�v�ȗv�f�ƂȂ��Ă��܂��B
�@�{�s�ł��A�Ɩ��������̂��߂̃f�W�^���c�[�������͕K�{�ł��B���ɁA�{�s�͐E�������������̂ɔ���Ȃ��ł��B�����I�ɋƖ��𐋍s���邽�߂ɂ́AAI��RPA�Ȃǂ�ϋɓI�ɓ������A�E���̕��S���y�����邱�Ƃ͂ƂĂ��d�v�ł��B�܂��A�f�W�^�����ɑ���E���̋���E�x�����p���I�ɍs���A�X���[�Y�ɐi�߂邽�߂̑̐��\�z�����߂��܂��BDX���i�̂��߂ɐ��I�Ȓm�������l�ނ��m�ۂ��A�K�v�ɉ����ĊO���̐��Ƃ▯�Ԋ�ƂƘA�g����d�g�݂𐮂���ׂ��ł��B�f�W�^���X�L�������ړI�Ƃ������C�v���O���������������A�����ł�DX���i�̐����\�z���邱�Ƃ��K�v�ł��B
�B�����A�g�ƃI�[�v���f�[�^���p�̐��i
�@�L�c�s�ł́A�I�[�v���f�[�^�̊��p�▯�ԂƂ̘A�g��ϋɓI�ɐ��i���Ă���A����ɂ��s���T�[�r�X�̌����V�������Ƃ̏ꂪ���܂�Ă��܂��B�s�����T�d�ȉۑ�̉����ɉ����������܂��B
�{�s�ł��A�I�[�v���f�[�^�̊��p�▯�Ԋ�ƂƂ̘A�g���������邱�Ƃ͗L�v���ƍl���܂��B���ɁA�f�W�^���Z�p�ɋ������Ԋ�ƂƂ̋��͂́A�V�����T�[�r�X������I�ȍs���^�c�̃��f����n�����A�s���ɂƂ��ėL�v�ȏ�����邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂��B