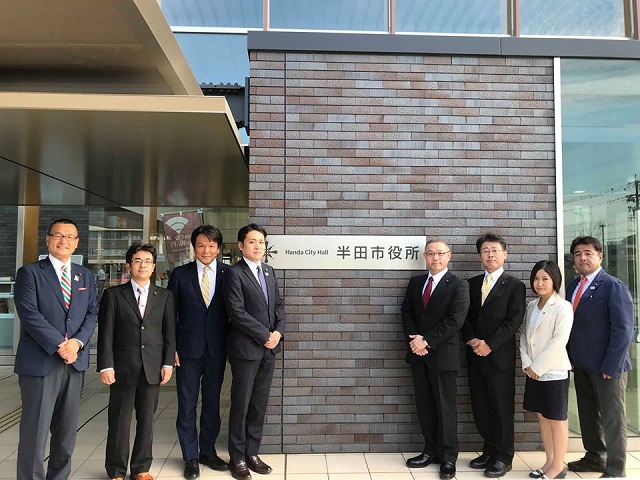現在位置 :トップページ › 行政視察報告書
各常任委員会、議会運営委員会、各会派 行政視察報告書
視察報告書
- 委員会名・会派名
- 前進かすかべ。未来の会
- 視察先
- 愛知県 半田市
- 視察案件
- マイレポはんだについて
- 実施日
- 平成30年10月2日
- 参加者氏名
- 小久保 博史、岩谷 一弘、栄 寛美、海老原 光男、古沢 耕作、山口 剛一、吉田 稔、永田 飛鳳
視察結果概要
(1)視察先の概要
半田市は、名古屋市の南、中部国際空港の東にあり、知多半島の中央部東側に位置しています。人口は、平成30年4月1日現在で119,428人、世帯数は50,668世帯、市域面積は47,42㎢。昭和12年に誕生し、古くから海運業、醸造業などで栄え、知多地域の政治・経済・文化の中心都市として発展してきました。
半田市の象徴としては、豪華絢爛な31輌の【山車】、半田運河沿いの趣のある【蔵】、童話ごんぎつねで知られる【新美南吉】、明治時代の息吹を伝える【半田赤レンガ建物】があります。
【山車】は精緻を極めた彫刻、華麗な刺繍幕、精巧なからくり人形などが備えられており、その祭りは300年余りの歴史があり、その伝統や文化を現在に受け継いでいます。5年に一度開催される「はんだ山車まつり」は勇壮な祭りイベントであり、半田が誇る31輌の山車が勢ぞろいし、大競演が繰り広げられます。
【蔵】は黒板囲いの酒造蔵が立ち並ぶ散策スポットとなっており、半田運河沿いは江戸の面影を残し、当時の風情を今へ伝えています。ほのかに酢の香りが漂う一帯は、環境省の「かおり風景100選」に選ばれています。
【新美南吉】は小学校の教科書でもおなじみの童話「ごんぎつね」の作者であり、半田に生まれ育ち、教員をしながら執筆をしていました。郷土をこよなく愛した作家で、彼の書いた物語には、ふるさとの豊かな自然、その中で生きる人々の思いやりや、やさしさが溢れています。「ごんぎつね」に登場する矢勝川沿いの堤では、毎年秋に300万本の彼岸花が咲き誇り、隣接する新美南吉記念館とともに多くの観光客で賑わいます。
【半田赤レンガ建物】は明治32年にカブトビールの製造工場として誕生しました。明治時代に建てられたレンガ建造物としては日本で五本の指に入る規模を誇り、国の登録有形文化財に登録され、平成27年からは観光拠点としてオープンしています。
(2)視察内容
半田市の「マイレポはんだ」は、スマートフォンを利用して、道路の陥没や施設の破損など、身近な問題を手軽に解決する先進的な取り組みです。そのシステムとして、まず、スマートフォンの無料民間アプリ(FixMyStreetJapan)を登録し、市民の方(投稿者)から町の問題を写真や、場所、状況を投稿してもらうことにより、インターネット上の地図に場所が表示されます。その後、市の担当者が投稿内容を見て対応します。「市民協働課所管」で主に管理されており、ルールとして、管理者1人を決め、出勤後・お昼・夕方で投稿を確認し、投稿されたものについては、投稿した翌日には必ずファーストメッセージ、返信を行います。
平成25年4月1日に放映されたNHK「クローズアップ現代」でFixMyStreetJapanを使用した千葉市の取り組みを基に半田市で検討開始し、実証実験を経て平成26年10月から運用がされています。
従来は、市民の方側から町で問題があったときに【どこに連絡すればよいかわからない】【役所が開いてる時間しか連絡できない】【電話では場所と状況が伝えにくい】【課題・問題に対してどのように対応しているかわからない】や行政側からは【道路パトロールや点検を実施しているが、見回りきれない】【電話では場所と状況が把握しづらい】【現地確認に時間がかかる】などの問題がありました。
「マイレポはんだ」による効果として、【スマートフォン・パソコンにより、いつでも簡便に課題・問題を伝えることができる】【写真・GPSデータにて、状況・場所を正確に伝えることができる】【みんなが対応状況を確認でき、行政対応の透明性を高めることができる】【自分のレポートにより町が改善されることで、地域への貢献ができる】【多くの人から情報提供を受けることで、行政の目が届かないところの課題・問題も把握できる】【行政側も現地確認の初動の効率化が図れる】ということを期待しているということです。
(3)視察から得られた考察
「マイレポはんだ」を導入することによる最大のメリットは、問題になっている位置がすぐにわかるという点です。それにより、早く現場の判断を行い対応することができます。電話では伝えられない情報を伝えることができ、またその後の進捗も確認が可能です。
この取り組みは、スマートフォンを活用している方に限られますが、仕事で忙しい働き盛りの世代や、あまり来庁する機会がない若い世代の方、またなかなか自治会などに加入できてない人の声を拾うことができるものだと感じました。開庁時間外でも24時間投稿ができる仕組み、ニックネームでの投稿も可能などSNSに慣れ親しんだ人に違和感なく浸透します。今後は若い人に積極的に参加してもらえば、全体の市民の満足度もあがり、また、地域の課題・問題などを若い世代にも身近に感じてもらえる1つのきっかけとして取り組みやすい事業であると考えます。
さらに、「マイレポはんだ」は災害時、災害本部が設けられると、災害版に切り替わり災害時の情報収集ツールとして利用が可能です。普段から使っているものに災害時のものを取り入れることで使用方法などに支障をきたさないという工夫も考えられていて、他にも様々な方面で活用できる可能性も秘めています。
今後の課題として大きなものは【市民の参加者が少ない、認知度が低い、市独自のアプリではないので市内の人の登録者がわからない】【解決のための市民参加・市民協働が難しい】ということです。
市が、行政が、自分たちの意見や問題をどう取り扱ってくれているのか、どう対応してくれているのかというのが目に見えてわかることで、より自分の街に興味を持ち、意識が向上していく効果も期待できる先進的な取り組みだと思うので是非本市でも実施検討して頂きたいです。また課題・問題を市民と行政が共有し、共に解決に向かっていくという考えを大切に参考にさせて頂きながら住みよい街を全員で作り上げていきたいです。
半田市は、名古屋市の南、中部国際空港の東にあり、知多半島の中央部東側に位置しています。人口は、平成30年4月1日現在で119,428人、世帯数は50,668世帯、市域面積は47,42㎢。昭和12年に誕生し、古くから海運業、醸造業などで栄え、知多地域の政治・経済・文化の中心都市として発展してきました。
半田市の象徴としては、豪華絢爛な31輌の【山車】、半田運河沿いの趣のある【蔵】、童話ごんぎつねで知られる【新美南吉】、明治時代の息吹を伝える【半田赤レンガ建物】があります。
【山車】は精緻を極めた彫刻、華麗な刺繍幕、精巧なからくり人形などが備えられており、その祭りは300年余りの歴史があり、その伝統や文化を現在に受け継いでいます。5年に一度開催される「はんだ山車まつり」は勇壮な祭りイベントであり、半田が誇る31輌の山車が勢ぞろいし、大競演が繰り広げられます。
【蔵】は黒板囲いの酒造蔵が立ち並ぶ散策スポットとなっており、半田運河沿いは江戸の面影を残し、当時の風情を今へ伝えています。ほのかに酢の香りが漂う一帯は、環境省の「かおり風景100選」に選ばれています。
【新美南吉】は小学校の教科書でもおなじみの童話「ごんぎつね」の作者であり、半田に生まれ育ち、教員をしながら執筆をしていました。郷土をこよなく愛した作家で、彼の書いた物語には、ふるさとの豊かな自然、その中で生きる人々の思いやりや、やさしさが溢れています。「ごんぎつね」に登場する矢勝川沿いの堤では、毎年秋に300万本の彼岸花が咲き誇り、隣接する新美南吉記念館とともに多くの観光客で賑わいます。
【半田赤レンガ建物】は明治32年にカブトビールの製造工場として誕生しました。明治時代に建てられたレンガ建造物としては日本で五本の指に入る規模を誇り、国の登録有形文化財に登録され、平成27年からは観光拠点としてオープンしています。
(2)視察内容
半田市の「マイレポはんだ」は、スマートフォンを利用して、道路の陥没や施設の破損など、身近な問題を手軽に解決する先進的な取り組みです。そのシステムとして、まず、スマートフォンの無料民間アプリ(FixMyStreetJapan)を登録し、市民の方(投稿者)から町の問題を写真や、場所、状況を投稿してもらうことにより、インターネット上の地図に場所が表示されます。その後、市の担当者が投稿内容を見て対応します。「市民協働課所管」で主に管理されており、ルールとして、管理者1人を決め、出勤後・お昼・夕方で投稿を確認し、投稿されたものについては、投稿した翌日には必ずファーストメッセージ、返信を行います。
平成25年4月1日に放映されたNHK「クローズアップ現代」でFixMyStreetJapanを使用した千葉市の取り組みを基に半田市で検討開始し、実証実験を経て平成26年10月から運用がされています。
従来は、市民の方側から町で問題があったときに【どこに連絡すればよいかわからない】【役所が開いてる時間しか連絡できない】【電話では場所と状況が伝えにくい】【課題・問題に対してどのように対応しているかわからない】や行政側からは【道路パトロールや点検を実施しているが、見回りきれない】【電話では場所と状況が把握しづらい】【現地確認に時間がかかる】などの問題がありました。
「マイレポはんだ」による効果として、【スマートフォン・パソコンにより、いつでも簡便に課題・問題を伝えることができる】【写真・GPSデータにて、状況・場所を正確に伝えることができる】【みんなが対応状況を確認でき、行政対応の透明性を高めることができる】【自分のレポートにより町が改善されることで、地域への貢献ができる】【多くの人から情報提供を受けることで、行政の目が届かないところの課題・問題も把握できる】【行政側も現地確認の初動の効率化が図れる】ということを期待しているということです。
(3)視察から得られた考察
「マイレポはんだ」を導入することによる最大のメリットは、問題になっている位置がすぐにわかるという点です。それにより、早く現場の判断を行い対応することができます。電話では伝えられない情報を伝えることができ、またその後の進捗も確認が可能です。
この取り組みは、スマートフォンを活用している方に限られますが、仕事で忙しい働き盛りの世代や、あまり来庁する機会がない若い世代の方、またなかなか自治会などに加入できてない人の声を拾うことができるものだと感じました。開庁時間外でも24時間投稿ができる仕組み、ニックネームでの投稿も可能などSNSに慣れ親しんだ人に違和感なく浸透します。今後は若い人に積極的に参加してもらえば、全体の市民の満足度もあがり、また、地域の課題・問題などを若い世代にも身近に感じてもらえる1つのきっかけとして取り組みやすい事業であると考えます。
さらに、「マイレポはんだ」は災害時、災害本部が設けられると、災害版に切り替わり災害時の情報収集ツールとして利用が可能です。普段から使っているものに災害時のものを取り入れることで使用方法などに支障をきたさないという工夫も考えられていて、他にも様々な方面で活用できる可能性も秘めています。
今後の課題として大きなものは【市民の参加者が少ない、認知度が低い、市独自のアプリではないので市内の人の登録者がわからない】【解決のための市民参加・市民協働が難しい】ということです。
市が、行政が、自分たちの意見や問題をどう取り扱ってくれているのか、どう対応してくれているのかというのが目に見えてわかることで、より自分の街に興味を持ち、意識が向上していく効果も期待できる先進的な取り組みだと思うので是非本市でも実施検討して頂きたいです。また課題・問題を市民と行政が共有し、共に解決に向かっていくという考えを大切に参考にさせて頂きながら住みよい街を全員で作り上げていきたいです。