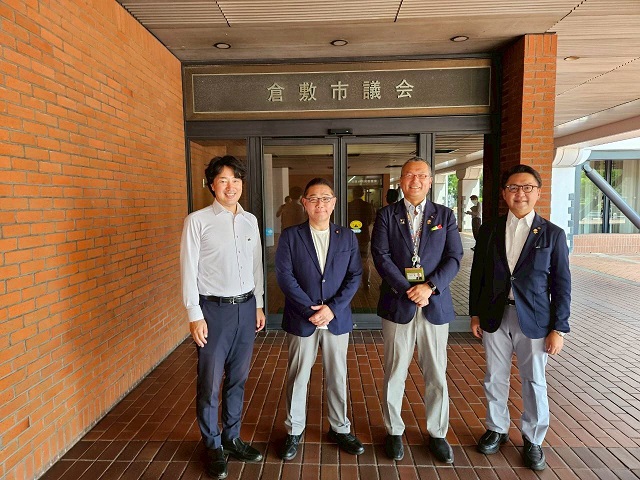現在位置 :トップページ › 行政視察報告書
各常任委員会、議会運営委員会、各会派 行政視察報告書
視察報告書
- 委員会名・会派名
- 次世代 かすかべ!
- 視察先
- 岡山県 倉敷市
- 視察案件
- 災害時の対応・対策について
- 実施日
- 令和7年7月10日
- 参加者氏名
- 小久保 博史、吉田 稔、伊藤 一洋、阿部 雅一
視察結果概要
(1)視察先の概要
倉敷市は岡山県の南部に位置し面積、356.07㎢、瀬戸内海に面し高梁川が市域を貫流する地理的特性があり、新幹線・山陽本線・伯備線・瀬戸大橋線などの鉄道網と、山陽自動車道・瀬戸中央自動車道といった高速道路網が市内で交差する広域交通の結節都市となっています。
令和7年6月末日現在における人口は、471,742人(うち外国人8,845人)。市章は倉敷の「クラ」を図案化したもので、横へ広がる翼は瀬戸内経済圏の中核都市として、産業・文化・観光の調和ある住みよい理想都市を目指して飛躍発展する姿を表しています。また、円は市民の団結と融和を象徴しています。市木である「くすのき」と市花「ふじ」は、市のシンボルにふさわしいもの、倉敷の気候風土に適したものなどの条件を制定委員会により検討し、数多くの候補の中から各3種に絞った後、市民投票などを経て制定され、市役所東側広場には藤棚が造られました。また、中核市移行(平成14年4月1日)などを記念し、「市木・市花」に続いて新たに自然と人間との共生のシンボルとして、市の鳥「カワセミ」が制定されました。
(2)視察内容
平成30年7月、西日本豪雨では、前線や台風7号の影響により、温かく湿った空気が流れ込み続けた影響で、西日本を中心に記録的な大雨となりました。
倉敷市では270.5㎜という観測史上1位の降水量を記録した他、岡山県内24市町村に初めて大雨特別警報が発表され、高梁川水系の矢掛・酒津・日羽水位観測所では氾濫危険水位を超過し、観測史上最高水位を記録しました。
倉敷市北西部に位置する真備地区においては、増水した高梁川に支流である小田川の水が流れ込めなくなる「バックウォーター現象」で水位が高い状態が長時間継続したことにより、小田川とその支流の堤防8カ所が決壊、7カ所で一部破損・損傷となり、真備地区4,400ヘクタールの約3割にあたる1,200ヘクタールが浸水し深さは最大で5mに及びました。
真備地区は過去においても度々大きな浸水被害に見舞われており、明治26年10月、昭和47年7月には堤防が決壊し、昭和51年9月には内水氾濫が発生するなどしたため、河川管理者の国土交通省において、抜本的な治水対策である「小田川合流点付替え事業」が、平成26年に事業化され、まさに平成30年秋の工事着手直前での豪雨災害でありました。
避難所についても、ピーク時に最大72カ所、避難者数は5,000人を超え、避難所の運営・環境整備や支援にあたっては他自治体や多くの民間団体などの支援が行われ、建設された仮設住宅は合計6カ所266戸、プレハブ建築協会、岡山県建築工事協会、岡山県宅地建物取引業協会、岡山県不動産協会、地権者などの協力で、借上型(みなし)仮設住宅は3,300世帯8,167人が入居しました。
この真備地区を中心とした甚大な浸水被害への取り組みが、災害発生時における初動対応から復旧・復興に至るまで、現在の倉敷市の多岐にわたる災害対策の基盤となっており、その様々な取り組みを視察させて頂き、春日部市として今後の災害対策への備え、危機管理体制の在り方について学ばせていただきました。
(3)視察から得られた考察
今回の視察を通じて、倉敷市の災害対策は、過去の経験から得られた教訓に基づき、多岐にわたる施策が各部署で連携できるよう対策を講じることの重要性が見られましたが、それには、市役所職員同士だけでは話が進まない実態がある中において、各地域の市議会議員や自治体トップの市長の政治判断による影響が大きいとの話から大変重要な示唆を与えられました。一例として、市長より市職員へ、市内の単身世帯高齢者の実態調査の指示が出され、その取り組みが進められているとのことであることから、春日部市においても、情報弱者や高齢者や障がい者など、情報収集や避難が困難な市民への支援体制は喫緊の課題であり、個別避難計画の作成支援や、地域住民との連携が強化できるような重層的な対策に取り組む必要性があります。特に地域コミュニティの連携強化については、更なる自主防災組織の育成支援や、学校教育を通じた防災意識の啓発は、災害時における共助の力を高める上で不可欠であり、地域特性に応じたきめ細やかな支援策の検討を進める上でも、ハザードマップを活用した実践的な防災訓練を定期的に実施し、地域住民が災害時の行動を具体的にイメージできるよう促すことが重要です。
倉敷市では、甚大な被害の経験から、河川改修などのハード対策と、情報伝達や防災教育などのソフト対策の取り組みがバランスよく進められており、春日部市においても、様々な考えられる対策を連携させ、相乗効果を高めるという視点がまず必要となります。
災害対策は、それぞれの地域特性によるものが大きいが、倉敷市の先進的な取り組みを参考にしつつ、春日部市の地域特性や課題に即した災害対策を進める具体的な検討と、住民の防災意識の向上と、地域社会全体で災害に対応する「自助・共助・公助」の体制強化が喫緊の課題であります。
最後に倉敷市においても、今後の取り組みとして大変重要な課題となっている「ペット防災」についても、全国的な課題として高まっていることを申し添えておく必要があります。
倉敷市は岡山県の南部に位置し面積、356.07㎢、瀬戸内海に面し高梁川が市域を貫流する地理的特性があり、新幹線・山陽本線・伯備線・瀬戸大橋線などの鉄道網と、山陽自動車道・瀬戸中央自動車道といった高速道路網が市内で交差する広域交通の結節都市となっています。
令和7年6月末日現在における人口は、471,742人(うち外国人8,845人)。市章は倉敷の「クラ」を図案化したもので、横へ広がる翼は瀬戸内経済圏の中核都市として、産業・文化・観光の調和ある住みよい理想都市を目指して飛躍発展する姿を表しています。また、円は市民の団結と融和を象徴しています。市木である「くすのき」と市花「ふじ」は、市のシンボルにふさわしいもの、倉敷の気候風土に適したものなどの条件を制定委員会により検討し、数多くの候補の中から各3種に絞った後、市民投票などを経て制定され、市役所東側広場には藤棚が造られました。また、中核市移行(平成14年4月1日)などを記念し、「市木・市花」に続いて新たに自然と人間との共生のシンボルとして、市の鳥「カワセミ」が制定されました。
(2)視察内容
平成30年7月、西日本豪雨では、前線や台風7号の影響により、温かく湿った空気が流れ込み続けた影響で、西日本を中心に記録的な大雨となりました。
倉敷市では270.5㎜という観測史上1位の降水量を記録した他、岡山県内24市町村に初めて大雨特別警報が発表され、高梁川水系の矢掛・酒津・日羽水位観測所では氾濫危険水位を超過し、観測史上最高水位を記録しました。
倉敷市北西部に位置する真備地区においては、増水した高梁川に支流である小田川の水が流れ込めなくなる「バックウォーター現象」で水位が高い状態が長時間継続したことにより、小田川とその支流の堤防8カ所が決壊、7カ所で一部破損・損傷となり、真備地区4,400ヘクタールの約3割にあたる1,200ヘクタールが浸水し深さは最大で5mに及びました。
真備地区は過去においても度々大きな浸水被害に見舞われており、明治26年10月、昭和47年7月には堤防が決壊し、昭和51年9月には内水氾濫が発生するなどしたため、河川管理者の国土交通省において、抜本的な治水対策である「小田川合流点付替え事業」が、平成26年に事業化され、まさに平成30年秋の工事着手直前での豪雨災害でありました。
避難所についても、ピーク時に最大72カ所、避難者数は5,000人を超え、避難所の運営・環境整備や支援にあたっては他自治体や多くの民間団体などの支援が行われ、建設された仮設住宅は合計6カ所266戸、プレハブ建築協会、岡山県建築工事協会、岡山県宅地建物取引業協会、岡山県不動産協会、地権者などの協力で、借上型(みなし)仮設住宅は3,300世帯8,167人が入居しました。
この真備地区を中心とした甚大な浸水被害への取り組みが、災害発生時における初動対応から復旧・復興に至るまで、現在の倉敷市の多岐にわたる災害対策の基盤となっており、その様々な取り組みを視察させて頂き、春日部市として今後の災害対策への備え、危機管理体制の在り方について学ばせていただきました。
(3)視察から得られた考察
今回の視察を通じて、倉敷市の災害対策は、過去の経験から得られた教訓に基づき、多岐にわたる施策が各部署で連携できるよう対策を講じることの重要性が見られましたが、それには、市役所職員同士だけでは話が進まない実態がある中において、各地域の市議会議員や自治体トップの市長の政治判断による影響が大きいとの話から大変重要な示唆を与えられました。一例として、市長より市職員へ、市内の単身世帯高齢者の実態調査の指示が出され、その取り組みが進められているとのことであることから、春日部市においても、情報弱者や高齢者や障がい者など、情報収集や避難が困難な市民への支援体制は喫緊の課題であり、個別避難計画の作成支援や、地域住民との連携が強化できるような重層的な対策に取り組む必要性があります。特に地域コミュニティの連携強化については、更なる自主防災組織の育成支援や、学校教育を通じた防災意識の啓発は、災害時における共助の力を高める上で不可欠であり、地域特性に応じたきめ細やかな支援策の検討を進める上でも、ハザードマップを活用した実践的な防災訓練を定期的に実施し、地域住民が災害時の行動を具体的にイメージできるよう促すことが重要です。
倉敷市では、甚大な被害の経験から、河川改修などのハード対策と、情報伝達や防災教育などのソフト対策の取り組みがバランスよく進められており、春日部市においても、様々な考えられる対策を連携させ、相乗効果を高めるという視点がまず必要となります。
災害対策は、それぞれの地域特性によるものが大きいが、倉敷市の先進的な取り組みを参考にしつつ、春日部市の地域特性や課題に即した災害対策を進める具体的な検討と、住民の防災意識の向上と、地域社会全体で災害に対応する「自助・共助・公助」の体制強化が喫緊の課題であります。
最後に倉敷市においても、今後の取り組みとして大変重要な課題となっている「ペット防災」についても、全国的な課題として高まっていることを申し添えておく必要があります。